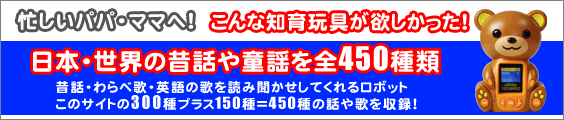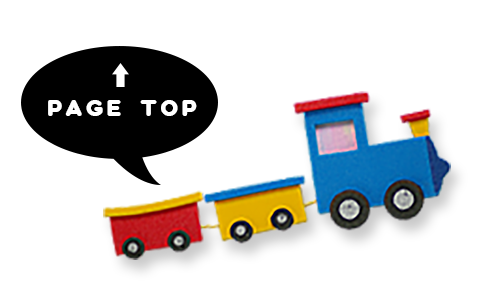<<前のお話 ブレーメンのおんがくたい | ヘンゼルとグレーテル | 次のお話 しらゆき姫>>
ヘンゼルとグレーテル
むかしむかし大きな森の入口に貧しい木こりがすんでいました。
木こりには、おかみさんと二人の子供がいました。男の子の名前はヘンゼル、女の子の名前はグレーテルといい、家は、その日食べるものさえないほど貧乏でした。
木こりは、ため息をついて、おかみさんに、
「うちの暮らしは、どうなるというのだ。食べ物もないのに、どうやって、あのかわいそうな子供たちを育てることができるのか?」
すると、おかみさんは、
「いい方法がある。明日の朝早く、子供たちを森の一番奥へ連れて行き、そこでたき火をたいて、私たちはそのまま仕事にいっちまう。子供たちには帰る道も分からないし、私たちも助かるというわけよ。」
「とんでもない。そんなこと、おれにはできない。自分の子供を、森の中へ置き去りにするなんてひどすぎる。すぐに獣がやってきて、子供たちを食い殺すにちがいない。」
木こりがそういうと、おかみさんが言い返しました。
「馬鹿だね。このままじゃ、四人とも飢え死にするんだよ。ふん、あんたなんか、私たちのかんおけの板でもけずっていればいいわ。」
「でも、子供たちがかわいそう・・・・。」
そのとき、子供たちは、お腹が空いて眠れなかったので、お母さんのいった言葉を聞いてしまいました。こんなことを平気で言えるのも、このおかみさんは子供たちの本当のお母さんではないからです。グレーテルは、涙を流しながらヘンゼルにいいました。
「私たち、もうおしまいだわ。」
「しっ、静かに!なくのはおやめ。僕が何とか助けてあげるから。」
ヘンゼルは、お父さんとお母さんが寝静まるのを待って、ベッドをおり、上着を着ました。戸を抜けて外へ出ると、
上着のポケットに詰め込めるだけの小石をひろい、部屋に戻りました。
「グレーテル、安心して。神様はきっと、僕たちを守ってくださるよ。」
次の日の朝、また太陽が昇っていないのに、おかみさんがやってきて、二人の子供をたたき起こしました。
「さあ、起きるんだよ。この怠け者たち。みんなで森へ薪を取りに行くんだから。」
それから、ふたりにそれぞれ一切れずつのパンを渡していいました。
「このパンは、お前たちの昼ごはんだからね。決してお昼前に食べるんじゃないよ。もうこれっきりだということを忘れないでね。」
四人はそろって、森の中へ入っていきました。しばらく行くと、ヘンゼルは立ち止まって、家の方を振り返りました。同じ事を何度も続けるので、お父さんが尋ねました。
「ヘンゼル、どうして何度も振り返っているんだい。」
「ああ、僕、白い猫を見ているんだ。僕の猫は屋根の上に座って、さよならを言おうとしているんだもの。」
と、ヘンゼルが言いました。
でも、本当は、ヘンゼルは猫を見ていたのではなく、立ち止まって振り返るたびに、ポケットから小石をひとっだし、道に投げていたもです。森も奥に来ると、お父さんが言いました。
「お前たち、ここでたき火をするから、薪を拾っておいで。」
ヘンゼルとグレーテルは薪を拾い集め、山のように積み重ね、薪に火がつき、炎が高く燃えがりました。
二人は長く座っているうちに疲れてしまい、居眠りを始めたかと思うと、そのままぐっすりと寝込んでしまいました。
目を覚ましたときには、もうあたりは真っ暗でした。
「どうしたら森から出られるの……」
グレーテルが泣き出しました。
「もう少し我慢してお待ち。ちゃんと帰り道が分かるから。」
まもなく満月が昇り始めました。ヘンゼルは、妹の手を引いて歩き始めました。投げておいた小石が銀貨のように光って、二人の行く道を教えてくれました。
二人は夜中じゅう歩き続けて、夜明けとともに家へたどり着きました。
「まったくじょうがない子達だね。どうしていまごろまで森で寝ていたのさ。お前たちはもう、家に戻りたくないのだと思っていたよ。」
おかみさんが残念がっていいました。
そんなことがあってまもなく、お母さんがお父さんに話す言葉を、またも子供たちが聞いてしまったのです。
「もう何もかも食べつくしまったわ。残っているのはパンが半分だけ。どうしてでも、子供たちに出て行ってもらわなきゃ。今度こそ、帰り道の分からないほど深い森に連れて行く。そうしないと、私たちおしまいよ。」
これを知ったヘンゼルは、二人が寝るのを待って、小石を拾いに行こうとしましたが、おかみさんがドアに鍵をかけてしまい、外へでることもできません。それでも、ヘンゼルは妹をなぐさめて言いました。
「ないたりしちゃだめだよ。神様はきっと、僕たちを守ってくださるから。さあ、お休み。」
次の日、朝早くやってきたおかみさんは、この前のときよりずっと小さい一切れのパンを渡すと、森へ急がせました。
行く道々、ヘンゼルは時々、立ち止まって後を振り返り、そのたびに、ポケットの中のパンを千切って地面へ投げました。
「ヘンゼル、どうして立ち止まっては振り返るんだね。」
「ああ、僕、こばとを見ているんだ。僕のこばとは屋根にとまって、さよならを言おうとしているんだもの。」
ヘンゼルが言うと、横からおかみさんが口を挟みました。
「馬鹿だね、あれはこばとなんかじゃない。屋根の上の煙突に指しているお日様よ。」
それでもヘンゼルは、パンがなくなるまで、次々土地面へ投げ続けました。
おかみさんは、子供たちを今まできたこともない森の奥へ連れて行き、前と同じように、大きなたき火をさせました。
「お前たち、ここに座っておいで。疲れたら少しぐらい眠ってもいいよ。お父さんとお母さんは、木を切りに言ってくるから。仕事がすんだら、迎えに来るからね。」
二人は、一切れのパンを分け合って食べ、それからまた眠り込んでしまいました。夕方が着ても、子供たちを迎えに来るものはいませんでした。二人は、夜中になって、やっと目を覚ましました。
「お月様が出たら、僕の投げてきたパンくずが見えるからね。そうすれば、ちゃんと帰り道を教えてくれる。」
月が昇ると、二人は歩き始めました。でも、どうしたのか、パンくずはどこにも見当たりません。
「大丈夫。きっと見つかるよ。」
ヘンゼルはグレーテルを励ましました。いくら歩いても、やっぱりパンくずはありません。なぜなら、森や野原の鳥たちが、ひとつ残らずパンくずを食べてしまったからです。ふたりは夜じゅう歩き続けました。次の日も、朝から晩まで歩きましたが、ついに森からでることはできませんでした。
道ばたで見つけたいちごのほかは、何一つ食べるものがありません。空腹とつかれのため、一歩も進めなくなり、木の下へ倒れこむと、たちまち眠り込んでしまいました。また歩き始めましたが、ますます森の奥へ入り込むばかりです。
歩いていると、一羽の真っ白な雪のようにきれいな小鳥を見つけ、二人が追いかけると、小鳥は一軒の小さな家の屋根にとまりました。近よってみると、なんと家はパン、屋根はお菓子でできていました。窓はすきとおったさとうです。
「さあ、すこしご馳走になろう。僕は屋根を一切れ、グレーテルは、窓を食べてもいいよ。」
いいながらも、ヘンゼルは我慢できずに屋根を一切れ千切りました。グレーテルは窓ガラスに近づき、ぽりぽりとかじりました。その時、家の中から、誰かきれいな大きな声で歌い始めました。
「ぼりぼり かりかり 私の家をかじっているのはどこの誰かしら。」
「それは風です。風です。」
二人は一緒に答えると、いらん顔で食べ続けました。そのおいしいこと、ヘンゼルは屋根を丸ごと一枚引き千切りました。グレーテルは窓ガラスを丸ごとはずすと、座り込み、二人で食べ始めました。
不意にドアが開いて、よぼよぼのおばあさんがふわりと出てたので、ヘンゼルもグレーテルもびっくりして、手に持っていたものを思わず落としてしまいました。
「おや、まあ、なんてかわいい子供たち。さあ、家に入っておいで。何にも怖い事はないからね。」
おばあさんは二人の手をとって、家の中へつれていき、ミルクに、りんごやくるみなどのごちそうが運ばれてきました。またまた夢中で食べ終わると、おばあさんは二人を寝室へ案内しました。
ヘンゼルとグレーテルは、ベッドへ横たわりました。まるで天国に来ているような気分でした。
でも、おばあさんの親切はうそで、本当は、子供たちを待ちぶせている恐ろしい魔女だったのです。あのパンの家も、子供たちをおびき寄せるためでした。
次の日の朝はやく、魔女は二人が目を覚ます前にもう起きており、眠っている子供たちを眺めながら、口をもぐもぐさせていいました。
「こいつは、おいしい料理になりそうじゃ。」
魔女は、ヘンゼルを抱きかかえると、小屋にはこびこみ、こうして戸を閉めて、鍵をかけました。目を覚ましたヘンゼルは、ないたり、わめいたりしましたが、まったくの無駄でした。
魔女は、再び子供たちの寝室へ戻り、グレーテルを起こして、大声でいいました。
「さっさと起きるんだよ。はやく水をくんできて、あんたのお兄ちゃんをふとらせるご馳走を作っておやり。うんと太ったら、私がいただくんだから。」
グレーテルは、わっと泣き出しましたが、いくらないてもどうにもなりません。恐ろしい魔女のいいなりになるしかなかったのです。
かわいそうなヘンゼルのために、ご馳走ができましたが、グレーテルに与えられたのは、かにのからだけでした。
魔女は毎朝、小屋に行って、
「ヘンゼル、指を出してごらん。どのくらい脂がのってきたか調べてやるから。」
ヘンゼルは、指のかわりに、転がっていた小さな骨をつきだしました。目の悪い魔女は骨とも気がつかず、どうして脂がのってこないのか、不思議で仕方ありませんでした。
こうして、ひと月がすぎ、ヘンゼルの指は、いつまでたってもかたくてやせたままでした。魔女は、グレーテルに向かって怒鳴りました。
「さあ、水をくんでおいで。ヘンゼルがふとっていようがやせていようが知るもんか。あしたこそ、料理してやるから。」
それをきいて、グレーレルは天を仰いで嘆き、涙を流して悔しがりましたが、仕方なく、水を運びながら叫ぶように言いました。
「神様、どうか、私たちを助けてください。こんなことになるなら、森の中で、獣に食われて死んだ方がましでした。」
「ないたり、さわいだりするのはおよし。」
魔女がいいました。
次の日の朝はやく、グレーテルはなべに水をはり、火を起こさせられました。
「そうそう、ご馳走を料理する前に、パンを焼かなくちゃ。パン焼きがまはあっためてあるし、粉もこねてあるし。。。。」
魔女は、いきなりグレーテルを捕まえ、かまどの前につきだし、
「さあ、かまどの中へお入り。もうパンを焼くのにいいかどうか、試すんだから。」
そういいながらも魔女は、グレーテルが中へ入れば、かまどのとびらをしめ、まる焼きにして食べるつもりでした。グレーレルは、さも困ったように、
「どうやってかまどの中へ入ればいいの。分からない。」といいました。
「馬鹿な子だね。かまどの口は、こんなに大きいじゃないの。ほら、私だってちゃんと入れる。」
魔女はよつんばいになり、パン焼きがまに頭をつっ込んで見せました。
(いまだわ!)
グレーテルは、魔女を力いっぱい押し込み、パン焼きがまのとびらをしめ、かんぬきをさしました。
「うぎゃぁぁぁーー!」
魔女は、カミナリが落ちてきたかと思うほどのさけび声をあげると、そのまま焼け死んでしまいました。
グレーテルは、まっすぐヘンゼルのいる小屋にかけつけ、戸をあけて叫びました。
「ヘンゼル、助かったのよ、私たち。あの魔法使いのおばあさん、死んじゃったわ。」
ヘンゼルは、まるでかごから解放われた小鳥のように、元気よく飛び出しました。二人は大喜びで、抱き合いながら、飛び回ったり、キスをしたりしました。
二人は安心して、魔女の家に入ってみると、あっちのすみにも、こっちのすみにも、宝石や真珠のぎっしりつまった箱がおいてありました。
ヘンゼルは、それをポケットにつめられるだけ、つめこみました。
「私も、おうちに待って帰ろう。」
グレーテルも、エプロン一杯につつみこみました。
「さあ、いこう。はやくこの恐ろしい魔女のいる森から抜け出さなくちゃ。」
二、三時間歩き続けると、森の様子がだんだんと見覚えのある景色にかわってきました。とうとう、懐かしいお父さんの家が見えました。
ふたりは思わず走り出し、家の中に飛び込むなり、お父さんに抱きつきました。
お父さんは、子供たちを森の中へおきざりにしてからというもの、楽しい時はなかったのですから。おかみさんはもう死んでいました。
グレーテルがエプロンをひらくと、宝石や真珠が部屋中に散らばり、ヘンゼルも、ポケットからつかみ出してまきちらしました。
これでもう、心配ごとは何一つなくなり、三人は何時までも楽しく暮らしました。
<<前のお話 ブレーメンのおんがくたい | ヘンゼルとグレーテル | 次のお話 しらゆき姫>>