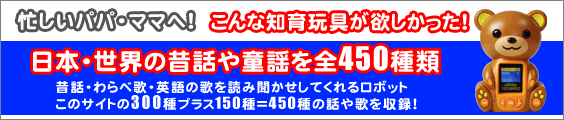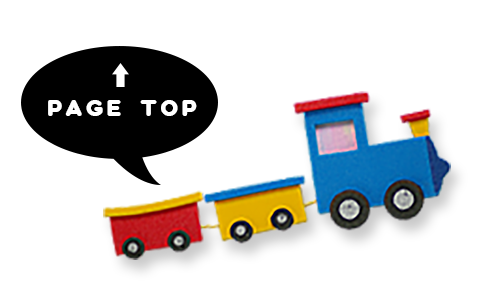<<前のお話 かいぞくだったおしょうさん | カガミのなかのひと | 次のお話 かさのえ>>
カガミのなかのひと
むかし、むかし、山奥に老人が住んでおり、数年前に妻を亡くし、今は息子と二人暮し、日中は畑仕事、ときには川釣り、夜は酒をたしなむという暮らしです。
ある日、老人は息子に言いました。
「そろそろ身を固めて所帯をもったらどうだな。いいか、わしはじきに死に、お前は一人になる。お前のことが心配だ。面倒をみてくれる女房が必要だ。」
村の人がさっそく隣り村の娘との縁談を用意してくれ、娘は、若くてたいそう美しく、一目でとりこになり、見合いのあと、息子は結婚することに決めました。
ほどなくして、父親が亡くなり、悲しさに打ちのめされ、若者は日を追うごとに落ち込んでいきくので、妻は夫を慰めようと京の都へお寺参りに行ってみてはどうかといいました。
「そうだな。京の都へ寺参りに行こう。親父のためだ。親父は死ぬ前に一度は京の都を見たい、とよく言っていたな。代わりに俺がこの目で見てきて親父の墓前で報告しようと思う。」
次の朝、若者は京の都に向けて旅立ちました。数日して京都に着き、神社を訪れ、有名なお城や庭も見物し、訪れる所どこでも父親を思い手を合わせ、父親も喜んでくれていると思うと心が軽くなりました。
ある日、若者はお店に寄ってお土産を買うことにしました。妻にかわいいくしを選んでいると、店の棚の上の金属製の鏡にふと目が留まりました。
「何とまあ、きれいな月が輝いているな!」若者は叫びました。実を言うと、生まれてこのかた鏡と言うものを見たことがなかったのです。
「手に取ってみて結構ですよ。」そう店の人が話しかけると、鏡を手に取り、中を覗いてみると、若者はびっくりして大声を出しました。
「父さん、何でこんな所にいるんだ。もう死んだはずだろう。でも生きてる、元気そうだ。それに、何と若いこと。口が動いているが、聞こえないぞ。一緒に家に帰ろう。」
「お気に入りましたか。すばらしい鏡でしょう。」
若者は、父親が見ず知らずの人に持っていかれるのではないかと心配になり、財布から持っていたお金を全部出して鏡を買いました。
元気なって家に戻った夫を見て、妻はほっとすると、夫は京の都で買ったきれいなくしを妻に渡しました。
夫のやさしさに感謝し、喜んで髪にさしました。一方、夫のほうは箱を持って納屋のほうへ行きました。
それからずっと、夫の様子はおかしく、毎朝、毎晩、納屋に入り、しばらく出てこなくなり、納屋から夫の声が聞こえてきました。それは毎日続いているので、若妻は心配でどうにもならなくなりました。
「どうして、そう足しげく納屋にいくのでしょう。」
ついに夫の居ない留守に、妻は納屋に入り、納屋をくまなく見回すと、納屋の片隅に金属製の鏡を見つけました。妻にははじめて見るもので、おそるおそる鏡を覗き込むと、女の人が見えました。ハッとしてまた女の姿を見て、妻は思わず息を呑みました。涙が出てきました。
「おんな、おんながこの中にいるわ!わかったわ。納屋に女を隠しているんだわ。こんなに若くて可愛い人。京都の舞妓か何かに違いないわ。頬は桃色で、唇は赤。素敵だこと!あら、顔をしかめたわ。夫がこんな女を隠しているなんて私は何と惨めな妻でしょう。」
それから夕方、夫が戻ってきて、家に足を踏み入れた途端、妻が台所で座って泣いているのに気がつきました。
「どうした。何かあったのか。」
「わかったのよ。あなたの秘密がわかったの。どうして黙ってたの。どうして納屋にこっそり女を隠していたの。私と同じ櫛をさしているわ。お前さんが私と同じものをあの女にもあげたのね。とても若くて可愛い女の人....。」
「女。ばかばかしい。親父だよ!」
妻は立ちあがると、大声で、
「お父さん?からかわないでよ。私、この目で女の人を見たわ。私と同じ櫛を挿した女がいたわ。」
「違う。親父だよ。有り金全部はたいて京の都で買ったんだ。」
「このうそつき!」
二人は喧嘩しつづけ、それを見た近所の人は止めようとしましたが、原因である鏡を見てみようとは誰も思いません。
やがて近所の人が物知りな尼さんに相談してみるよう言われたので、二人は箱に入った鏡を持ってお寺の尼さんを訪ねると、一部始終を話しました。
尼さんは箱を開け、鏡を手に取ってじっと覗き込み、そして、
「確かに女がこの中にいる。かわいそうに、この女、表情にかげりがあり、頭を丸めている。おそらく世の無常を悟り、意を決して仏に仕える身になったのでしょう。今は静かな部屋に座っているようです。私がこの鏡を預かり、この女の人にお経の読み方と座禅の仕方を教えてあげましょう。二人とも家に帰りなさい。そして仲直りしなさい。」
家路に向かう途中、妻が言いました。
「ねえ。私の言うとおりだったでしょう。」
「うん、そうだな。でもどうして親父は尼さんと知り合いになったのかな。俺の知ってる限りでは、親父は、仏さまを信じたことはなかった。」
尼さんは鏡を生涯ずっと宝物として手元に置いておきましたとさ。
<<前のお話 かいぞくだったおしょうさん | カガミのなかのひと | 次のお話 かさのえ>>